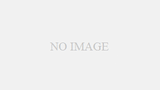こんにちは、辻せいやです。
前回は、「宅建を取って本当によかった」と思う理由をお話ししました。
今回は宅建試験の構成や配点、科目ごとの特徴について解説していきます。
■ 「どの科目から手をつけるべき?」という方へ
-
「合格ラインって何点くらい?」
-
「どれが一番点が取りやすいの?」
そんな疑問がある方にとって、**勉強の“地図”**になる内容です。
■ 宅建試験は全50問、マークシート方式!
宅建試験は、全50問の**四肢択一式(マークシート)**で行われます。
試験時間は2時間。1問あたり約2分強と、意外と時間に余裕はありません。
■ 科目構成と問題数の目安
| 科目 | 問題数(=配点) |
|---|---|
| 宅建業法 | 20問(20点) |
| 民法等(権利関係) | 14問(14点) |
| 法令上の制限 | 8問(8点) |
| 税・その他 | 8問(8点) |
※すべて1問1点、合計50点満点です。
■ 合格点は?絶対評価じゃないの?
宅建試験は相対評価です。
「○点以上で全員合格」ではなく、全体の上位15〜17%程度が合格する仕組みです。
そのため、合格点は年度によって変動しますが、35〜38点前後が目安になります。
ちなみに、これまでの最高合格点は38点(令和2年度10月実施試験)です。
■ 宅建業法からスタートがおすすめ!
得点源にしやすく、出題傾向も安定しているのが**「宅建業法」**。
-
配点が20点と大きい
-
過去問と似た形式が多い
-
比較的暗記中心で対策しやすい
まずはここを押さえるのが、合格への最短ルートです。
■ 一方で、民法(権利関係)はつまずきやすい
「民法」は抽象的な問題が多く、一度つまずくと沼にハマりやすい科目です。
避けたくなる気持ちもわかりますが、実は合格を左右する超重要パート。
後回しにしすぎず、早めに基礎に触れておくのがポイントです。
■ 勉強の順番を決めるだけで、かなり楽になる
試験に向けてまずやるべきなのは、「科目ごとのボリュームと難易度の見極め」。
これを知っておくだけで、勉強に対するストレスがぐっと減ります。
■ 「満点を狙う」必要はありません!
私が初めて宅建試験を受けたとき、
「全部理解しないとダメなんじゃ?」と完璧主義になりそうでした。
でも実際は…
✅ 苦手分野は切っても合格できる
✅ 取るべき問題(業法など)を確実に取る戦略が大事
この割り切りが、合格のカギになります。
■ 次回は「宅建業法」の最初のつまずきポイントを解説!
次回からは、宅建試験の主要4科目を1つずつ深掘りしていきます。
まずは、得点源になりやすい「宅建業法」からスタート!
-
「覚えることが多すぎる…」
-
「どうやって暗記すれば?」
そんな疑問に、私なりの乗り越え方を詳しくお話ししていきます。
■ 最後に
勉強法に迷っている方も、これからスタートしようとしている方も、
**「宅建って、ちゃんと道筋があるんだ」**と思ってもらえたらうれしいです。
次回の投稿もお楽しみに!