こんにちわ!辻せいやです。
前回のブログでは、宅建試験の効率的な勉強法として
過去問 → 解説 → AIで疑問解消 → 教科書で補強
という学習サイクルを紹介しました。
今回はその実例として、宅建試験の過去問をAIに聞いてみた結果をお届けします!
今回取り上げる問題
令和5年(2023年)宅建試験 問38(宅地建物取引業法)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。
イ宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。
ウ建設業者Bが、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当しない。
エ宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
AI(ChatGPT)による解説結果
ChatGPTに、「この過去問の回答と解説をよろしく!」と入力したところ、
下記の回答と解説が作成されました!
【ア】正しい
宅建業法における「宅地建物取引業」とは、売買・交換・代理・媒介のいずれかを反復継続して行う行為を指します。
「自ら貸す行為」は宅建業に該当しないため、この記述は正しいです。
【イ】誤り
「宅地建物取引士」になるには、
-
宅建試験合格
-
都道府県知事の登録
-
取引士証の交付
のすべてが必要です。
この記述は「取引士証の交付」に触れていないため不正確です。
【ウ】誤り
建設業者であっても、宅地の売買の媒介を業として(反復継続的に)行う場合は宅建業に該当します。
目的が建築請負であっても関係なく、媒介行為を行うなら免許が必要です。
【エ】正しい
宅建業法第15条の3では、宅地建物取引士に対して、
「知識及び能力の維持向上に努めなければならない」
という努力義務が定められています。
記述は正確です。
結論:正しいものは「2つ」(ア・エ)
教科書でも必ず確認しよう!
AIで疑問を整理したあとは、教科書で知識を補強することが大切です。
特に以下のテーマは毎年のように出題されます。
-
宅建業の定義
-
取引士の資格要件
→ 「うろ覚え」になりやすい部分は、繰り返し読むことで定着させましょう。
例:「反復継続して」とは?AIで聞いてみた!
ちなみに今回は、問題の回答と解説をAIに尋ねてみましたが
実際の過去問題集には、すべての問題に解説が付いています。
ですので、AIを活用する主な場面は、
「解説を読んでも意味が分からないとき」や「教科書に載っていない細かい疑問が出てきたとき」になると思います。
今回はその一例として、【ア】の選択肢に出てきた「反復継続して」という表現について、AIに聞いてみました。
AIの回答例:「反復継続して」とは?
「反復継続して」とは、
同じ行為を繰り返すこと、または
継続的に行う意思や実態があることを指します。
つまり、一度限りの取引ではなく、今後も同様の行為を続けていく意思・実態があるかどうかがポイントです。
具体例で確認!
-
自宅を一度だけ売却した場合
→ ❌ 反復継続していない(宅建業に該当しない) -
複数の不動産を繰り返し売却している場合
→ ✅ 反復継続している(宅建業に該当する可能性あり) -
自己所有のアパートを多数の人に貸している場合
→ ✅ 反復継続しているが、**「自ら貸す行為」**は宅建業には該当しない
このように、条文や用語の意味を補足的に調べたいときにAIは非常に便利です。
過去問や教科書だけでは理解が曖昧になりがちな部分も、AIに聞くことでクリアになることがあります。
まとめ:AIは疑問整理に最適なツール!
今回のように、
-
解説がわかりにくいとき
-
教科書に載っていない細かい疑問があるとき
-
条文や用語の意味を深く知りたいとき
AIはとても頼れる存在です。
疑問を放置せず、すぐに解決することで、理解と記憶の定着が一気に深まります。
次回も、AIを活用した宅建試験の勉強法や過去問解説をお届けします。お楽しみに!
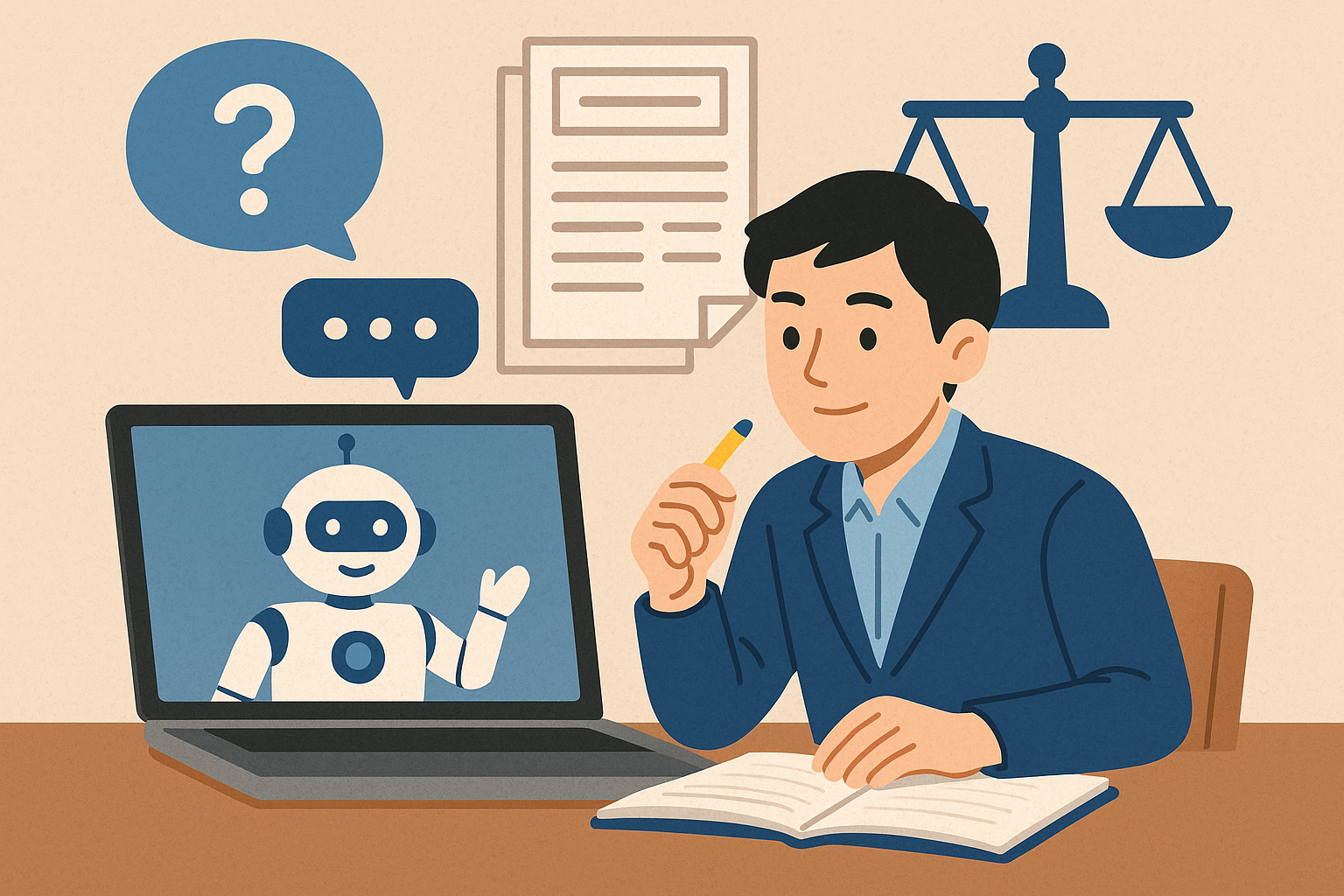
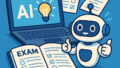
コメント