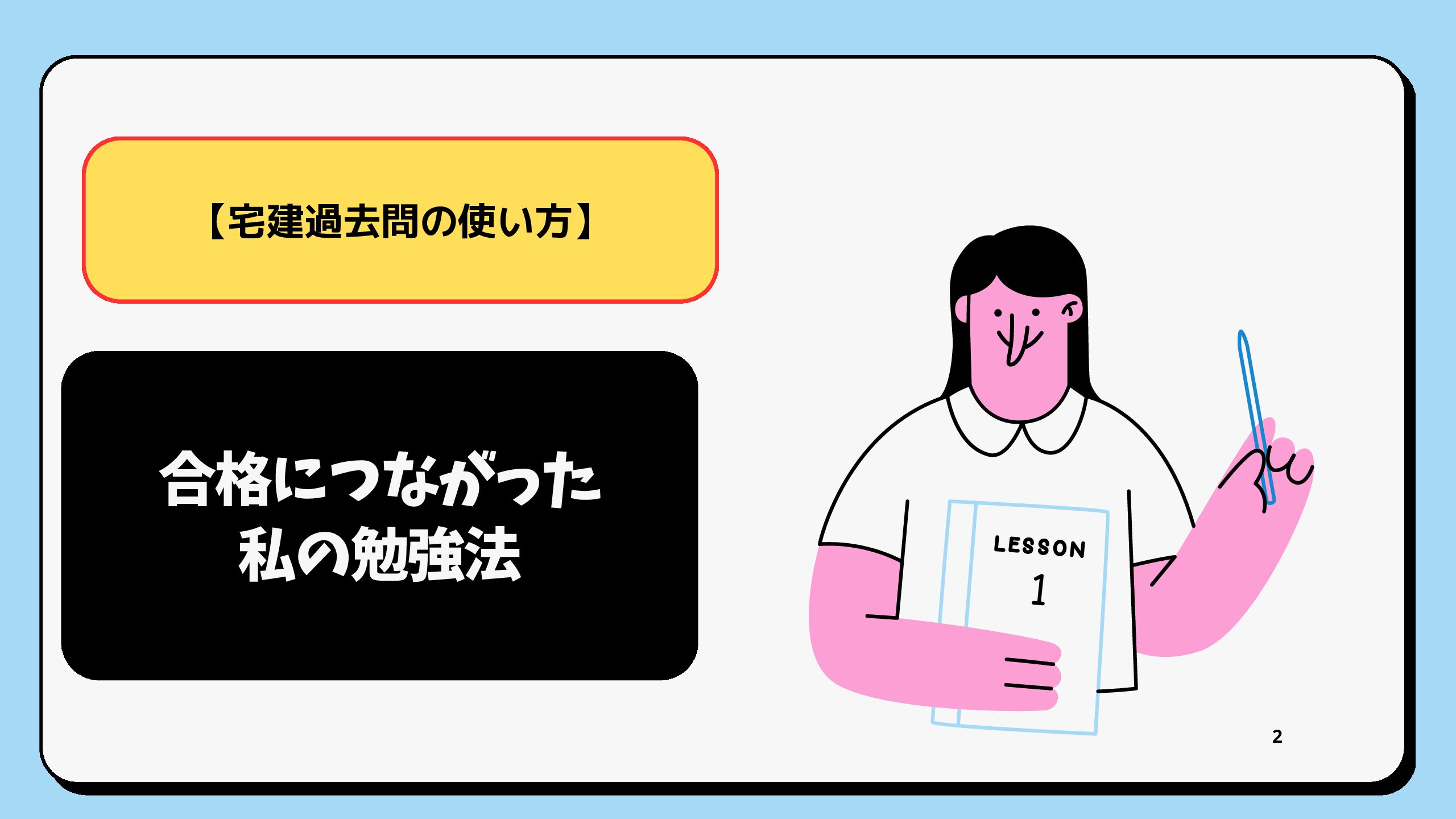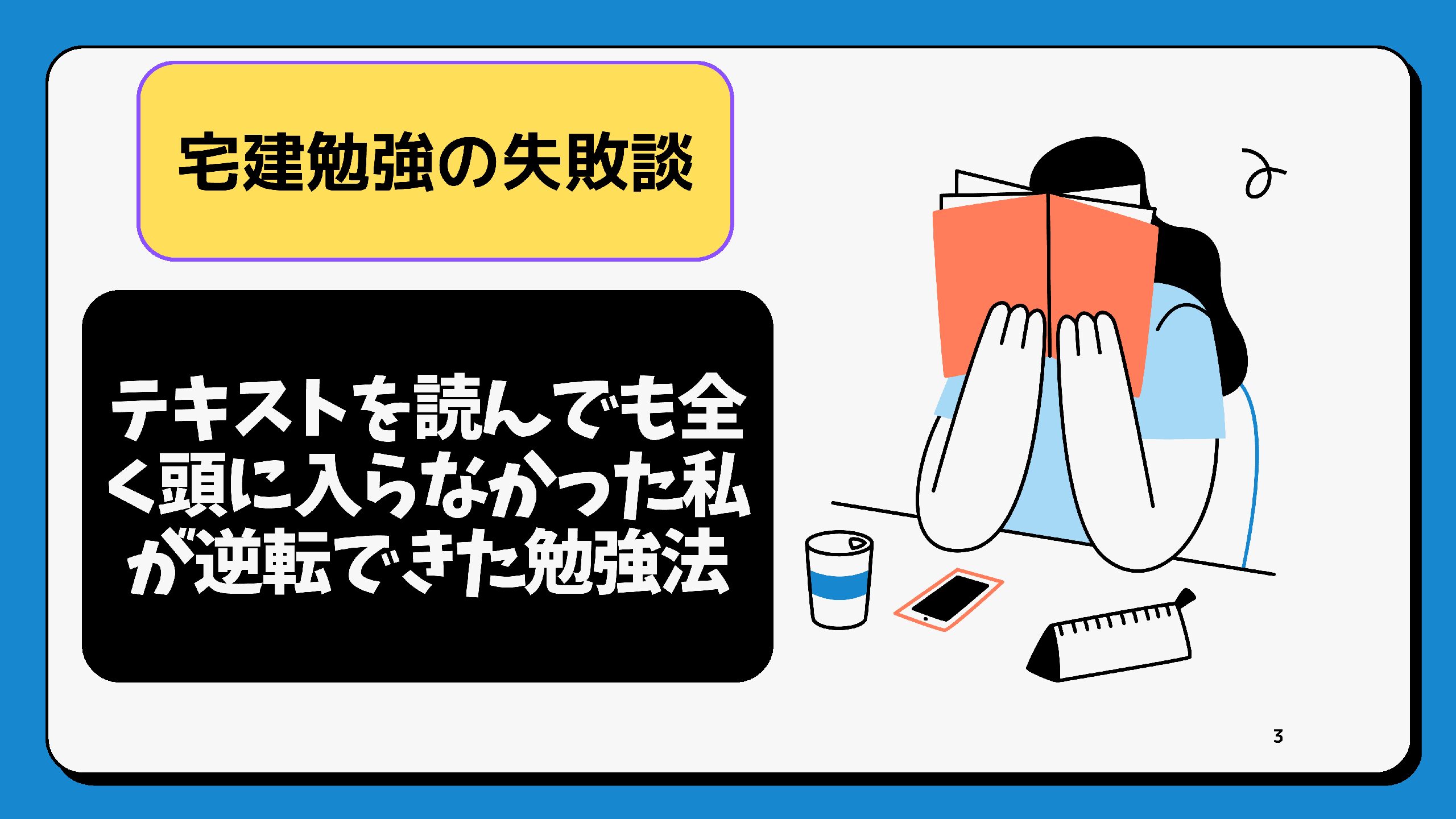こんにちは、辻せいやです。
今回は、私が宅建の勉強で最も大事にしていた「過去問の使い方」についてお話しします。
これから宅建試験にチャレンジする方に、少しでもヒントになれば嬉しいです。
「過去問は何年分?」「何周するの?」という疑問
宅建試験の勉強を始めると、必ず出てくるのがこの疑問です。
-
何年分の過去問を解けばいいのか?
-
同じ問題を何度もやるべきか?
-
解けるようになったら、次に何をすればいいのか?
私自身、最初はこうしたことに迷いながら進めていました。
でも実際に取り組む中で、自分に合ったやり方が見えてきました。
【前半】1冊の問題集を繰り返して土台をつくった
勉強を始めたばかりの頃は、テーマ別に整理された1冊の過去問集を使っていました。
この段階では「浮気せず、1冊を何度も解く」ことを重視。
最初は全く正解できなくても、「解説を読み込んで、テキストで確認する」というサイクルを繰り返すうちに、少しずつ知識が身についてきました。
問題を解くたびに、「あれ?これ前にも見たような気がする」という感覚が増え、
違う年度でも似た論点が繰り返し出題されていることに気づきました。
この「よく出るテーマ」に慣れることで、宅建試験の全体像がつかめてきたんです。
【後半】年度ごとの過去問50問で“本番慣れ”と総仕上げ
基礎がある程度固まってきた段階で、僕は次のステップに進みました。
それが、**過去10年分ほどの年度別問題(50問形式)**を実際に解くという方法です。
これは、以下の目的でとても効果的でした:
-
本番と同じ形式に慣れる(50問を通して解く体力や集中力を養う)
-
実力の確認と、苦手分野の洗い出し
-
宅建独特の「引っかけ方」や「クセ」の確認
ここで得点力を実感できたことが、自信にもつながりました。
年度をまたいで繰り返すことで、パターンが見えてくる
複数年分の過去問を解いてみて改めて感じたのは、
出題形式や問われる論点がかなり似ているということです。
たとえば:
-
宅建業法は「35条書面」と「37条書面」が頻出
-
民法は「意思表示の取消」や「時効」が何度も登場
-
法令上の制限は「用途地域」「建ぺい率」「容積率」の計算問題が定番
違う年度で似た問題を繰り返し見ることで、自然と知識が整理され、記憶が深まりました。
私がやってよかった過去問勉強のまとめ
-
【前半】テーマ別問題集で基礎固め(繰り返し解く)
-
【後半】年度別50問で本番形式に慣れる(10年分ほど解く)
常に意識していたこと:
-
問題の「正解」より「出題の意図・パターン」に注目
-
間違えた問題に印をつけて、後で重点的に復習
まとめ:宅建試験は「見慣れる」ことで強くなる
宅建は、知識量だけでなく**「出題のされ方」に慣れる**ことがとても大切です。
そのためには、違う年度の過去問に繰り返し触れ、同じテーマに何度も出会うことが効果的でした。
私の場合、ただ同じ問題を何周も解くよりも、
“違う形で同じ内容が出てくる”ことに気づく経験が、合格に直結したと思っています。
次回予告
次回は少しだけ立ち止まって、
**「私がなぜ宅建を受けようと思ったのか?」**という原点を振り返りたいと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!