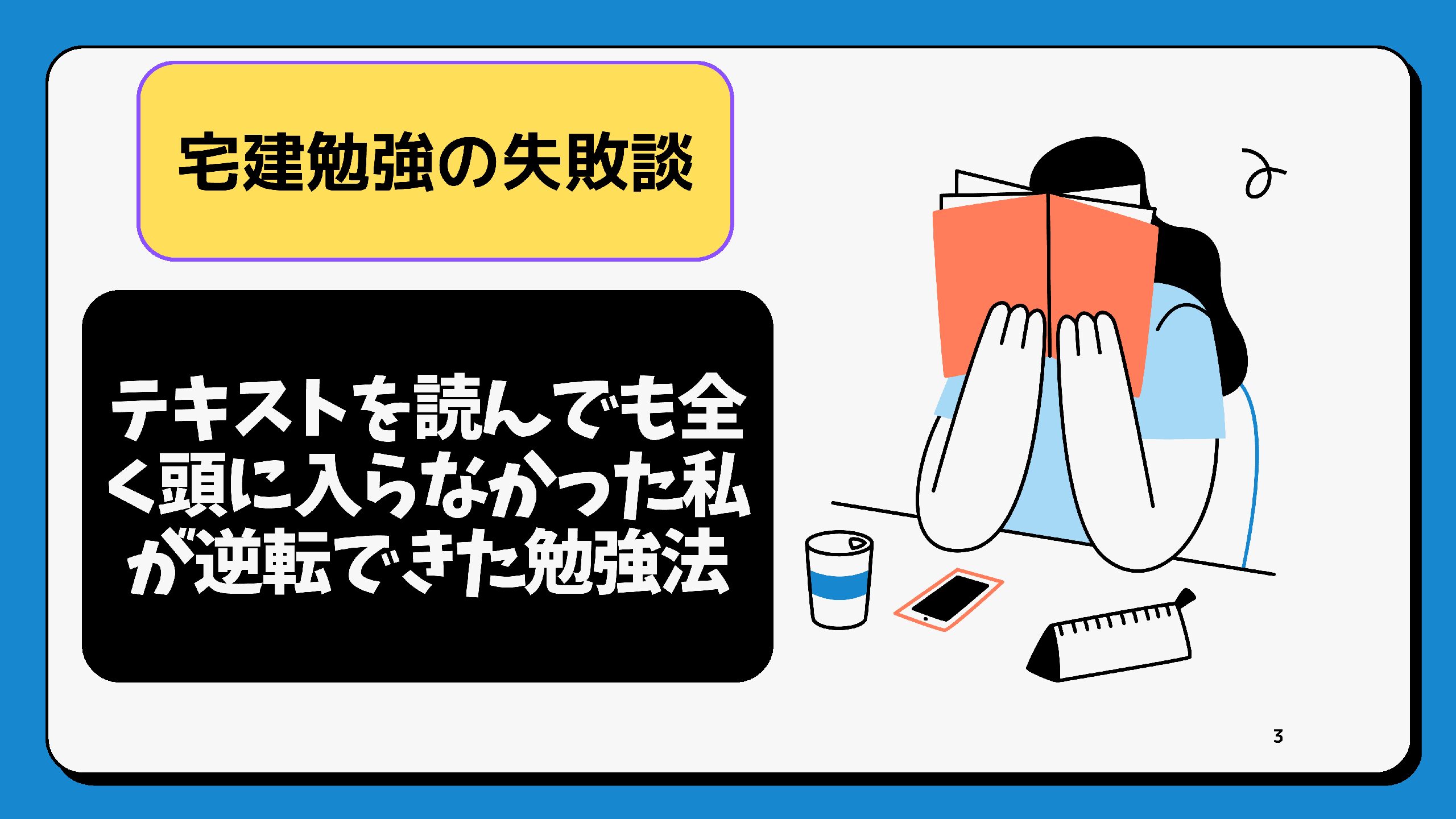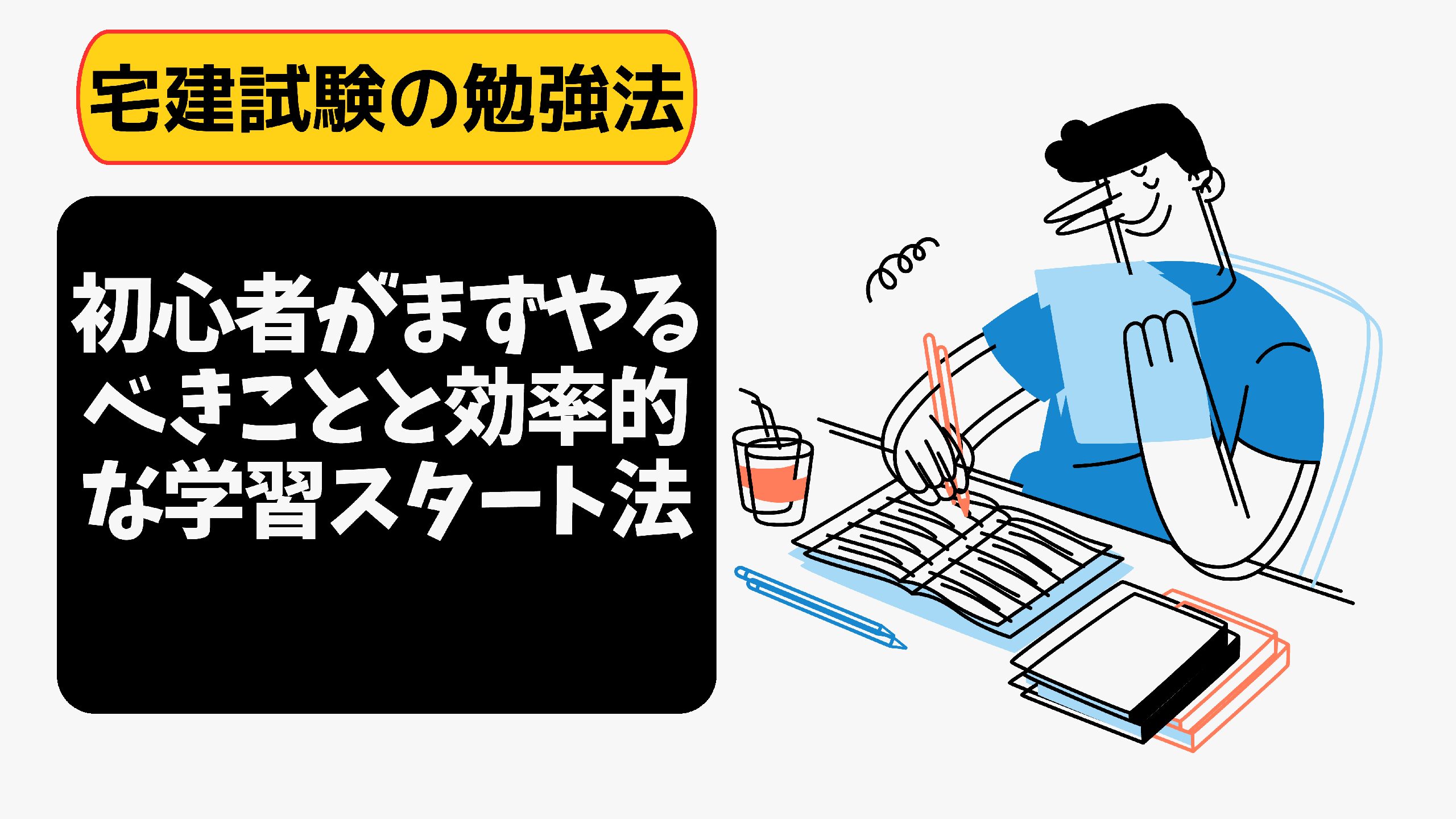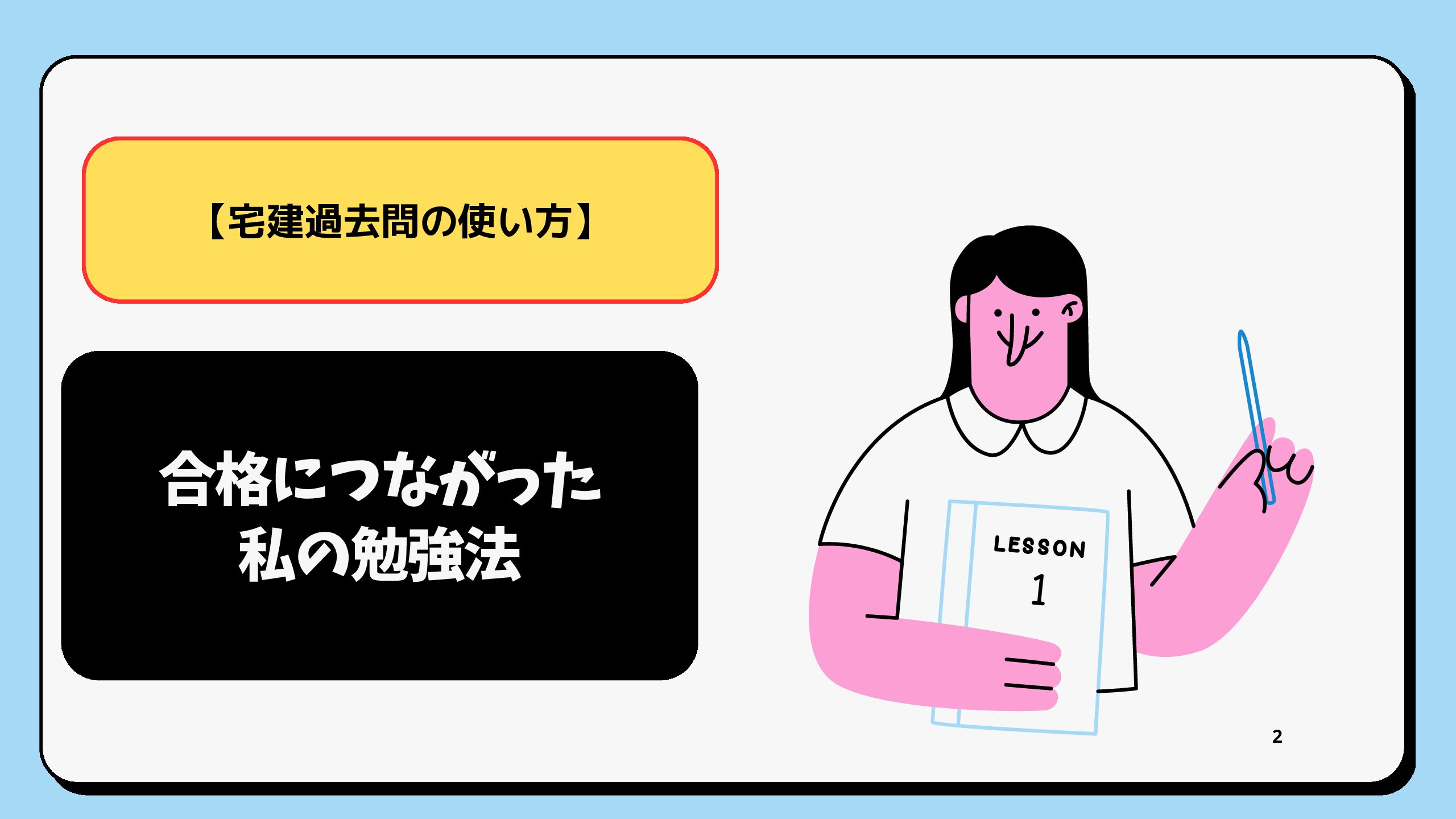こんにちは、辻せいやです。
今回の投稿では、私自身が宅建の勉強を始めたときに最初につまずいたこと、そしてそこから抜け出すためにたどり着いた学習の順番についてお話しします。
【最初のつまずき:テキストがまったく頭に入らなかった】
宅建の勉強を始めたばかりの頃、私は「まずはテキストをしっかり読んでから、過去問に取り組もう」と考えていました。
しかし、いざ始めてみると…。
テキストを読んでも、全く理解できなかったのです。
私は不動産業界未経験だったこともあり、宅建の基本テキストに書かれている内容がほとんど頭に入ってきませんでした。
聞き慣れない法律用語や専門用語、まったくイメージできない制度や数字の羅列…。
読み進めるたびに「これは一体、誰向けの文章なんだ?」と感じることばかりで、ページをめくるたびに集中力が途切れてしまいました。
【逆転のきっかけ:「問題を先に解く」勉強法】
ある日ふと、「このままじゃ進まない」と思い、気分転換のつもりでいきなり過去問を解いてみたんです。
もちろん正解できませんでした。
でも、解説を読んでみると少しだけ内容が頭に入ることに気づきました。
そしてその直後にテキストを読み返すと、
「あ、さっきの問題で出てたこの話のことか!」
と、少しずつ内容のつながりが見えるようになってきました。
【私に合っていた勉強の順番】
それ以来、私は勉強の流れを完全に変えました。
-
過去問を解く
-
解説をじっくり読む
-
教科書で該当箇所を確認する
この**「問題 → 解説 → テキスト」**というサイクルを回すようになってから、教科書の内容がぐっと身近に感じられるようになり、理解もスピードも格段に上がりました。
【宅建試験は「出され方」を知ることが大事】
宅建の試験問題は、毎年パターンが似ている部分も多く、ある程度**「出題のクセ」**があります。
過去問を通して「こういう形で問われるのか」を知ると、自然と教科書の内容が試験にどう活きるのかが見えてきます。
知識を頭に入れる前に、「出され方」を知っておくことで、学ぶ意味がハッキリするんです。
【テキストが難しく感じているあなたへ】
「読んでも理解できない」「全然進まない」――そう悩んでいる方もいるかもしれません。
でも、それはあなたの理解力が足りないからではありません。
むしろ、宅建のテキストは最初から読むには誰にとってもハードルが高い構成になっているんです。
だから、やり方を少し変えるだけで、見える世界が変わります。
【まとめ:勉強の順番を変えるだけで、学びやすさが変わる】
宅建の勉強に「正解」はありませんが、
**「まず問題に触れてみる」**ことから始めると、学びの流れが自然に生まれてきます。
僕のようにテキストでつまずいた方は、ぜひ一度、
**「問題 → 解説 → テキスト」**の流れを試してみてください。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
今後も、あなたの勉強が少しでも前に進むような情報をお届けしていきます。